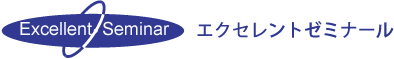2023-07-04
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:社会編
前回は南米で発見された銀を資金源としてスペインが富強となったが、やがてイギリスがスペインにとって代わるようになる、という話をしました。世界的な覇権の流れを見ると、スペイン⇒オランダ⇒イギリス⇒アメリカ合衆国と移って行きます。
シュサイ:「前回は、
南アメリカの
ボリビアの
ポトシ銀山が発見されたことで、
スペインが
「太陽の沈まぬ国」として繁栄したというお話をしたね。そして、
スペインが
銀に頼るあまり、
国内産業の育成を怠って、やがて
覇権から滑り落ちたことも話したね。
スペインは
ネーデルラントの独立運動で打撃を受けたから衰退したんだけれど・・・・・当時
スペインには
無敵艦隊(>>
詳しくはこちら)と呼ばれる
最強艦隊があって、これを破って勝つのは至難の業といわれていた。これを破ったのが
イギリス海軍だった。これら
スペインと
イギリスの海戦を無敵艦隊の名にちなんで、
アルマダの海戦(>>
詳しくはこちら)と呼ぶんだ。」
C君:「たしか、そんな話だったな。」
シュサイ:「キミたちにとってはピンとこない話が多いとは思うけど・・・・・漫画「世界の歴史」を読むと流れがわかることがあるように、こういう話を下敷きにしたマンガを読んで理解を深め、世界史に興味を持つことも大事だよ。」
B君:「・・・・・というと?」
シュサイ:「たとえば、フランス革命を題材にしたマンガって何か知ってる?」
A子:「もしかして、ベルばら?」
シュサイ:「そう。
池田理代子作の
「ベルサイユのばら」(>>
詳しくはこちら)だ。もちろん
フィクションだけど、ある程度の
歴史的背景を頭に入れるためにはマンガは有効だよ。ちなみに、この
スペインと
イギリスの戦いをマンガにしたものでは、
青池保子作の
「七つの海七つの空」(>>
詳しくはこちら)、
「エル・アルコン-鷹-」、
「テンペスト」があって、いずれもなかなか面白いよ。これらの話は
宝塚歌劇団で上演されているから・・・・・
「ベルばら」しかり、
「エル・アルコン-鷹-」しかり、
原作が面白いことは証明ずみだということだろう。また、同じく
青池保子作の「
アルカサル-王城-」は
中世スペインの話で、これも面白いから、受験が終わったら読んでみるといいよ。」
C君:「先生ってマンガよく読むの?」
シュサイ:「面白いマンガはね。他にも
大和和紀作の
「あさきゆめみし」(>>
詳しくはこちら)などは、
源氏物語のあらすじを理解するには良いと思うよ。
麻生元首相じゃないが、個人的は
「ゴルゴ13」もおすすめだけどね。あれはマンネリ化を避けるために、ベースとなる話をいろいろな
脚本家に依頼して、かなり
最近の事情を取り入れた話にしているから。」
B君:「ふ〜〜ん、そうなんだ。」
シュサイ:「さて、とにかく16世紀〜18世紀のヨーロッパは、「出る杭は打たれる」というヤツで、スペインVSオランダ、フランスVSイギリス、イギリスVSスペイン・フランス連合、そしてプロイセン(ドイツ)やオーストリア、ロシアなどまで入り乱れて、戦いの連続だった。ナポレオンもこの頃の人物で・・・・・いろいろと面白い逸話も多いんだが・・・・・経済の話に絞るのがテーマだから、ちょっと時代を戻して1600年の話をしよう。」
B君:「1600年というと、関が原の戦いですか?」
C君:「国が会社を作ったの??」
シュサイ:「当時の会社という概念と今の会社という概念はかなり違うんだ。会社には、株式会社や有限会社(特例有限会社)、合名会社、合資会社、合同会社があるんだが・・・・・詳しいことはさておき・・・・・一般的に会社といえば株式会社のことを指すが、世界で初めての株式会社はオランダ東インド会社だといわれているんだ。つまり、投資をして利益が上がったら株主に利益を分配するというしくみはこの頃に生まれたということだね。」
B君:「なるほど。官営会社みたいなものですね。」
シュサイ:「そういうことだね。日本だって、八幡製鐵所(>>詳しくはこちら)は初めは明治政府の殖産興業政策の一環として官営製鐵所として作られ、その後民間に払い下げられたでしょ。つまり、何のかんの言っても、政治と経済は切っても切れない関係なのさ。というわけで、時間がきたから、今日はここまでとしよう。」
2023-06-27
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:社会編
さて、前回は大航海時代の話をしましたが、経済がグローバル化するのはこれ以後になります。さて、どのように世界は変化してきたのでしょうか・・・・・・
シュサイ:「前回は
大航海時代の話をしたわけだが・・・・・もともとは
インドから
香辛料を直輸入するために、
ポルトガルとスペインが競争した結果、
大航海時代となったわけだ。だから、はじめは
コロンブスの
アメリカ大陸発見は、重視されなかったんだが・・・・・・それ以後は
探検の時代から
征服の時代へと変化していった。つまり新大陸の原住民を征服し、そこを
植民地としていったわけだ。
スペインは
インカ帝国や
アステカ帝国を滅ぼしたが・・・・・原住民たちが
インディオとかインディアンと呼ばれるのは、
スペイン語や
英語で
インド人という意味だからなんだ。
ポルトガルとスペインによる
新航路開拓と海外領土奪取競争が激化し、他のヨーロッパ諸国も
海外進出を始めた。当時の
スペインは「
太陽の沈まない国」(>>
詳しくはこちら)と呼ばれたんだよ。」
C君:「太陽が沈まないって、どういうこと??」
シュサイ:「
世界中に植民地があったことを指すたとえだよ。
ヨーロッパにある本国で太陽が沈んだとしても、その裏側に
植民地があれば、太陽は沈まないでしょ。
世界中に植民地があることと、繁栄している事をかけた言葉なんだ。
「太陽の沈まない国」と呼ばれた国は、
スペイン帝国(>>
詳しくはこちら)と
イギリス帝国(
大英帝国 >>
詳しくはこちら)があって・・・・・
世界の覇権はスペインからイギリスへと移っていくことになるんだが・・・・・ここらへんの話は面白いから、少し詳しく見ていくことにしよう。」
A子:「難しそう・・・・。」
シュサイ:「女の子にはあまり興味が無いかも知れないけど・・・・・帝国の興亡の歴史は、面白いよ。実際、ガンダムしかり、スターウォーズしかり、帝国の興亡の歴史が下敷きとなっているストーリーは多いからね。」
C君:「ダースベーダーが出てくるの?」
シュサイ:「
ダースベーダーは出てこないけれど・・・・・
特徴ある歴史上の人物は登場するよ。その筆頭が
イギリスの
ネルソン提督(>>
詳しくはこちら)だな。」
B君:「聞いたことがあるな。」
シュサイ:「ネルソン提督はフランス革命のときのコルシカ攻略戦で片目を失い、カナリア諸島の戦いで右腕を失っていて、隻眼隻腕のイギリス海軍提督として有名なんだ。そして、イギリスとスペインが覇権を争ったトラファルガーの海戦で、勝利したけれども・・・・・敵の狙撃手に撃たれて、艦上で戦死したんだ。そして、そのとき遺した言葉が「神に感謝します。私は義務を果たしました。」というものだったそうだ。」
B君:「う〜〜ん。ドラマだなあ。」
シュサイ:「さて、話を元に戻そう。大航海時代の後、16世紀中頃〜17世紀前半はスペインが最も繁栄した時代で「黄金の世紀」と呼ばれる。なぜこんなに発展したかというと・・・・・南米のボリビアに世界有数の銀の埋蔵量を誇るポトシ銀山が見つかり、スペインが開発したからなんだ。ポトシ銀山を発見し、インディオたちに強制労働させて、安価な銀を大量に採掘した。そして、その銀をヨーロッパに運び、その銀でアジアから香辛料や綿や絹を購入した。つまり、大航海時代⇒大陸の発見⇒貿易独占政策によりポルトガルが、ついでスペインが富強となる、という流れなんだ。メキシコ・ペルーの征服は莫大な金・銀・宝石類をスペインにもたらした。ところが、この銀が大量にもたらされたことで、当時の重要国内産業である毛織物工業をおろそかにした。ところがそのうちネーデルラントで独立運動が起こって、これによって膨大な戦費を使うハメになったスペインは斜陽化するんだ。」
シュサイ:「そう。ネーデルラントは低地地方という意味で、現在のベルギー・オランダ・ルクセンブルクを合わせた地域、つまりベネルクス三国のことだと思って良いよ。さて、このあたりの話はかなり政治的・宗教的にもいろいろあるので省いて・・・・・無敵艦隊の話とトラファルガーの海戦の話に行きたいんだけど・・・・・時間が無いから次回にしよう。」
というわけで、次回はあまり経済の話とは関係ないのですが、個人的に好きなところなので、スペインVSイギリスの話とトラファルガーの海戦の話をしたいと思います。それでは、また。
2023-06-20
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:社会編
前回は東方貿易でもてはやされたのがコショウを中心とする香辛料であることを書きました。今回は大航海時代の大陸発見について詳しく見ていきましょう。
シュサイ:「前回は、ルネサンスの三大改良によって、羅針盤・火薬・活版印刷が実用化され、それにしたがって
大航海時代(>>
詳しくはこちら)が到来したことを話したね。」
B君:「はい。でも・・・・・羅針盤はわかるけど、火薬や活版印刷って大航海時代とどう関係するんですか?」
シュサイ:「いい質問だね。まず、火薬だが・・・・・船には大砲があるよね?」
B君:「あ! なるほど。」
シュサイ:「そう。未知の航海に旅立とうとする船が丸腰じゃ心もとないしね。で・・・・・活版印刷なんだが、世界一のベストセラーは何だったっけ?」
A子:「聖書です。」
シュサイ:「そう。
活版技術が
グーテンベルク(>>
詳しくはこちら)によって実用化され、まず
聖書が印刷されたんだ。それまでは
僧侶だけが読む環境にあった
聖書が広く世間で読まれるようになると、
聖書に関して
違う解釈をする人が現れ、
宗教改革と呼ばれる運動をすることになったんだ。これが現在の
プロテスタント派で・・・・・だから
プロテスタント派の宗派を
新教と呼び、それまであった
カトリック派を
旧教と呼ぶんだ。そして
カトリック派はその後、
イエズス会を結成し、
海外布教活動を重要視した。この
イエズス会の創立者の一人が、
日本史にも出てくる
フランシスコ・ザビエル(>>
詳しくはこちら)だよ。」
B君:「へ〜〜、そうなんだ。」
シュサイ:「だから、
羅針盤と
火薬と
活版印刷は実は密接な関係があるのさ。さて、話をもとに戻そう。1488年に
ポルトガルが後ろ盾となって、
バルトロメウ・ディアスが
喜望峰に到着したよね。すると、負けてはいられないと思った
スペインが
コロンブス(>>
詳しくはこちら)を遠征に出した。
コロンブスは
地球は丸いから、アフリカの最南端である喜望峰を経由しなくてもインドに着くはずだと主張したんだ。そして、
1492年に
アメリカ大陸を発見した。
「いよ〜〜、国(1492)が見える」と覚えると良いよ。」
C君:「一発で覚えた!」
A子:「はいはい、良かったわね。」
シュサイ:「そのため、
コロンブスは辿り着いた場所は
新大陸ではなく、
インドだと思っていたわけだ。だから、今の
バハマ諸島などを含む島々を
西インド諸島(>>
詳しくはこちら)と呼ぶんだよ。」
C君:「なるほど。なるほど。」
シュサイ:「そして、
ポルトガルは
1497年に
ヴァスコ・ダ・ガマ (>>
詳しくはこちら)に命じて、
喜望峰を回って
インドの
カリカットまで航海させる。これによって、
ヴァスコ・ダ・ガマは
東インド航路を発見し、
香辛料を
ポルトガルに持ち帰った。それまでは
インドと
香辛料の取引をするには
イスラム商人を経由しなければならなかったから、高くついていたわけだが、これによって
インドから直接輸入することができるようになってポルトガルは儲かったのさ。一方、
コロンブスが辿り着いたのは
バハマ諸島(>>
詳しくはこちら)だったわけだから、
香辛料はあるはずもない。したがって、どうもおかしいと思った
スペインは、
1501年に
アメリゴ・ヴェスプッチ(>>
詳しくはこちら)を派遣する。そして、
コロンブスが辿り着いたのが
東アジアではなく新大陸であることが明らかにされたわけだ。
アメリカという名前は、この
アメリゴ・ヴェスプッチが由来だから覚えておいてね。」
A子:「ふ〜〜ん。」
シュサイ:「その後、
スペインは
1509年に
マゼラン(>>
詳しくはこちら)に命じて
世界一周の航海をさせる。
出発時は256名いた乗組員が、戻ってきた3年後には18名に減っていたそうだ。
マゼラン自身も
フィリピンで原住民の酋長に殺されたんだ。でもこの航海によって、
地球が球体であることが証明されたわけだ。ちなみに、当時の
スペイン王子は
フェリペ(>>
詳しくはこちら)という名前なんだが・・・・・
フィリピンというのはこの
フェリペにちなんでつけられた。
南アメリカ大陸の南端の海峡を
マゼラン海峡(>>
詳しくはこちら)と呼ぶことも覚えておこうね。じゃあ、今日はここまでにしよう。」
というわけで、これで大航海時代と大陸発見を駆け足で書きましたが・・・・・探検って本当に命がけですね。それでは、次回もこの続きです。
2023-05-30
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:社会編
前回は産業革命によって、生産力が飛躍的に向上したというお話を書きましたが、政治と経済がグローバル化したのは15世紀末の大航海時代が発端です。そこで、今回は大航海時代の話をしたいと思います。
シュサイ:「前回は産業革命によって生産力が飛躍的に向上したという話をしたけど・・・・・経済的な発展を成し遂げるためには、貿易が不可欠なんだ。どんなにいいものを作ったところで、買ってくれる相手がいなかったら儲からないからね。つまり、産業革命が1733年からの100年ぐらいだと考えると、その時代にはすでに生産力を上げて大量生産をしても、製品を作ったら買ってくれる相手がいたことになるよね。そこで、少し時代をさかのぼって、当時のヨーロッパの様子を見てみよう。」
A子:「難しそう・・・・・日本史すら苦手なのに。」
B君:「オレは、漫画「世界の歴史」を読んでいるから少しはわかるかも・・・・・」
A子:「そうよね。いつも授業の合間に読んでいるもんね。どうせ私は・・・・・」
シュサイ:「日本史にも関係するから、覚えておくといいよ。鉄砲が日本に伝来したのはいつだっけ?」
B君:「以後予算、だから1543年です。」
シュサイ:「そうだね。どこの国の船が種子島に漂着したんだっけ?」
B君:「ポルトガルです。」
シュサイ:「そうだね。当時のヨーロッパは
大航海時代(>>
詳しくはこちら)と呼ばれて、いろいろな国が
探検家を送り出したんだが・・・・・先陣を切ったのが
ポルトガルなんだ。まず、
ポルトガルの後ろ盾で、
バソロミュー・ディアス(
バルトロメウ・ディアス >>
詳しくはこちら)が
ヨーロッパの南にある
アフリカ大陸の南端である
喜望峰まで達したのが
1488年のことだ。実はなぜ
大航海時代が訪れたかというと、この時代の
ヨーロッパは文化的には
ルネサンス(>>
詳しくはこちら)の時代で・・・・・
ルネサンスの三大発明とされているのが
羅針盤と
火薬と
活版印刷なんだ。」
C君:「おお、ルネッサ〜ンス!」
B君:「髭男爵じゃねえ!」
C君:「じゃあ・・・・・ログ・ポースの発明?」
B君:「ワンピースでもない! お前グランドラインに沈めるぞ!」
シュサイ:「わかった、わかった・・・・・・知ってる言葉に反応するのは悪いことではないんだが・・・・・2008年の北京オリンピック(夏季)の開会式でもやっていたけれど、実はこの三つとも中国で発明されたもので、世界史の教科書では「三大改良」と表記するものもあるんだ。つまり、中国での発明が草原の道(ステップ・ルート)、オアシスの道(オアシス・ルート、狭義のシルクロード)、海の道(マリン・ルート)の三つの経路で西洋に伝わり、発展したわけだ。さて、ここで問題です。その頃のヨーロッパで、最も高く売れた東洋の特産品は何でしょう?」
B君:「陶器かな? いや、お茶や絹製品かな?」
シュサイ:「それらも高く売れたんだが・・・・・最も必要とされたのは
コショウ(>>
詳しくはこちら)だ。
ヨーロッパ人は
肉を良く食べるわけだが・・・・・
肉の調理には塩と胡椒は欠かせないから、
東南アジアの
香辛料はすごく珍重されたんだ。
コショウには強力な
殺菌・抗菌作用があるから、
冷蔵技術が無かった時代にはすごく珍重されて、
金や
銀の重さと
同重量で交換されていた時代もあったほどなんだよ。
お茶の葉(>>
詳しくはこちら)も
運んでいる途中で変化したんだ。
お茶の葉が
緑色をしていれば緑茶(不発酵茶)、
ある程度発酵したお茶の葉がウーロン茶(青茶:半発酵茶)、
完全に発酵したお茶の葉が紅茶(完全発酵茶)だが・・・・・何ヶ月もかけて
ヨーロッパへ
お茶の葉を運んでいるうちに
発酵したのが
紅茶なわけだ。だから、イギリスでは
午後の紅茶(アフタヌーンティー)を楽しむ習慣があるわけだが・・・・・げっ・・・・もう時間が来ちゃった。しょうがない、続きは次回にまわそう。」
というわけで、次回は本格的に大航海時代の話に入ります。それでは、また。
2023-05-09
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:社会編
前回は、自給自足経済が商品経済に発達する過程を俯瞰(ふかん)しました。経済が大幅に発展したのは産業革命以降の話になりますので、ここからは少しゆっくりと経済の歴史を書いていきたいと思います。
シュサイ:「前回は、
農業中心の自給自足経済から少しずつ生産力が向上して、
市場経済が発達したという話までしたんだったね。
生産力が飛躍的に向上するには、
産業革命(>>
詳しくはこちら)を待たなければならなかったわけだが・・・・・
産業革命期に発明されたものにはどんなものがあるか知っているかい?」
B君:「たしか、ジェニー紡績機とか・・・・・」
B君:「公害だなあ。喘息(ぜんそく)になりそうですね。」
C君:「人権侵害で訴えてやる。」
A子:「はいはい、わかった、わかった。ちょっと黙っててくれる?」
シュサイ:「
アークライト(>>
詳しくはこちら)は
水力紡績機を発明しているけど・・・・・当時は
公害や
エコロジーの概念は無いから、まあ仕方ないな。ちなみに、
産業革命といっても数年の間に起こったわけではなく、およそ
100年間ぐらいかけて発展したんだ。」
C君:「遅っ!!」
A子:「あんただったら1000年かけても無理よ!」
シュサイ:「遅いように感じるかもしれないけど、自給自足経済時代が15世紀ごろまで続いていて、その後の商品経済時代が15〜18世紀の400年だとすると、たった100年で飛躍的に進歩したんだよ。蒸気機関車ができるまでは、移動手段はせいぜい馬なんだから。」
B君:「それはそうだなあ。」
シュサイ:「ところで・・・・・蒸気機関がはじめて利用されたのが紡績機だといえるわけだが・・・・・そのころの紡績機は何の糸をつむいでいたのかな?」
C君:「知ってる! カイコ!」
A子:「あんた、バカぁ?」
C君:「え、何で? 違うの?」
A子:「・・・・・ほんとに、バカね。」
B君:「へ〜〜、イギリス人って着物を着てたんだ?」
C君:「あっ、そうか。 ということは・・・・・」
シュサイ:「ヒツジの毛、つまり羊毛だね。その後は綿花になるけどね。」
C君:「いやあ、当然じゃないですか。わざと間違えただけですよ・・・・・皆わかってないなあ。」
B君:「ウソをいうな、ウソを。」
シュサイ:「・・・・・ハァ・・・・・・当時は毛織物工業がすごく儲かったんだ。なぜ儲かったかという話は・・・・・時間がきたから、次回にするか。」
というわけで、産業革命は
ジョン・ケイ(>>
詳しくはこちら)が
飛び杼(とびひ)を発明してから、
ニューコメン(>>
詳しくはこちら)や
ワットの
蒸気機関の改良を経て、
蒸気船や
蒸気機関車(>>
詳しくはこちら)が実用化されるまでの
およそ100年間を指します。この時期の
生産技術の進歩と
当時の社会のしくみが
どのように関わっていたか、という話も大事な話ですので、次回に少し詳しく書いていくことにします。それでは、また。
2023-04-18
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:社会編
アメリカで2つの銀行が経営破綻するような昨今ですが・・・・・中学受験生にとって、一番理解しにくい内容が経済の話だといえます。もともと経済の概念自体は高校の政治経済で詳しく学習する単元ですから、しかたがないのですが・・・・・現代を生きる人間としては、経済問題を避けて通れないので、小学生にもわかるように経済の概念やしくみについて書いてみたいと思います。
シュサイ:「最近、株が上がったとか下がったとか、円安だとか騒いでるけど・・・・・わかる?」
A子:「わかるような、わかんないような・・・・・」
シュサイ:「そうだよね。資本主義経済が本当はどういうものかがわかってないから、当たり前だね。でも、そこがわからないと経済のしくみがわからないから、初めて聞く言葉が多くて難しいかもしれないけど、数回に渡って経済の話をしよう。まず世界的に見ると、中世封建社会ぐらいまでは自給自足経済だったんだ。たとえば、平安時代や鎌倉時代には荘園の大きさが財力を示す基準だったけど、それを耕す農民たちがいて、はじめて米が収穫できるわけだよね。だから土地と農奴が財産だったといえるんだが・・・・・生産力の低かった当時は、その土地から収穫できる作物は、自分たちが生活するだけの分を作って消費する自給自足経済と変わらなかったんだ。つまり、社会全体で生産したものを社会全体で消費するだけで、生活自体が向上したわけではないんだ。」
B君:「なるほど。確かに当時は、
土地や
人の奪い合いが戦いの原因だから、
御恩と奉公(>>
詳しくはこちら)の関係が成り立つのか。」
シュサイ:「そう。ところが日本と違って陸続きのヨーロッパでは、15世紀〜18世紀ごろに商業資本家と呼ばれる商人たちが台頭して、商品経済(市場経済)が発達した。つまり、農産物を買い取って商品として他で高く売ったり、職人たちの同業組合(ギルド)が作った手工業製品を商品として扱って、職人を支配して儲ける人間が出てきたわけだ。」
シュサイ:「そうだね。日本の
座はヨーロッパの
ギルドに比べるとかなり規模が小さいけれど、同じだと思って良いよ。さてヨーロッパでは
他国と国境を接していることや、すぐ近くに
イギリスという島国があったこと、中国からの
シルクロードが通じていたことなどの理由で
貿易がすごく発達した。そして土地に束縛されている農民と違って、
商人たちは移動ができるから、ヨーロッパでは
商業都市が発達したんだ。日本でも
伝統工芸品で有名な町はあるけど、ヨーロッパの都市は
城壁に囲まれたり、
自治権があったりしたことで、日本の都市とは全然イメージが違うんだ・・・・・まあ、こういう話をすると本筋からそれてしまうから割愛するけど・・・・・ようするに、
農業主体の
自給自足経済から、
手工業製品主体の
商品経済へと移行し、
貿易が盛んになったことや
貨幣が流通するようになったこともあって、
市場経済(>>
詳しくはこちら)が発達したわけだ。」
C君:「要は、農業よりも商業の方が儲かるということか!」
A子:「あんた、それしか言わないよね。」
B君:「まあ、第一次産業が天候などの理由で不安定なのは当たり前だから・・・・・でも、第二次産業を飛び越して、第三次産業の商業が発達している気がするなあ。」
シュサイ:「いいところに気がついたね。自給自足経済が商品経済に移行するためには、生産力の向上が不可欠だよね。つまり、自分の食べ物を誰か他の人が作ってくれるから、食べ物以外の手工業製品を作ることに専念する職人が生まれる。だから、農業の生産性が向上したことが手工業製品の生産と流通を促したことになる。でも、よく考えてごらん。農業製品も手工業製品もすべて人の手が関わっているよね。つまり、人間が作る以上、一日に生産できる個数はおのずと決まってしまう。だから、工業が爆発的に発展するためには、産業革命が不可欠だったんだ。」
B君:「なるほど。日本史だけを勉強しているとそういう動きはわからないもんなあ。」
シュサイ:「蒸気機関の発明や紡績機の発明などによって、爆発的な生産力の向上があって、はじめて本格的な工業が発達したわけだが・・・・・時間がきたから、続きは次回にしようかな。」
というわけで、一気に中世と近世の経済体制を概観しました。産業革命以降が資本主義経済と呼ばれる経済体制になるわけですが、ここからは少し細かく時代を句切って見ていくことにします。それでは、また。