2023-01-31
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:理科編
前回、
動物についての第1回として
節足動物について書きましたが、
中学入試で圧倒的に出題されるのは、昆虫に関する問題です。これは、現在生存している種の半分以上が昆虫だからです。そこで数回にわたり、
昆虫に関して詳しく見ていくことにします。(>>
詳しくはこちら)
まず、
昆虫の分類のしかたについて見てみましょう。昆虫を分類するときには、
翅(はね)に注目して分類します。(>>
詳しくはこちら)
①カブトムシの仲間(鞘翅目:しょうしもく >>詳しくはこちら)・・・・・甲虫と呼ばれる昆虫で、飛ぶときに使う本来の後翅(うしろばね)が鞘(さや)である硬くなった前翅(まえばね)の内側にしまわれているところから、鞘(さや)の翅(はね)を持つ種類として分類されています。
②
チョウやガの仲間(鱗翅目:りんしもく >>
詳しくはこちら)・・・・・
チョウや
ガは翅(はね)に
鱗粉(りんぷん)や毛で覆われています。チョウやガの翅の色がキレイな色をしているのは、この鱗粉のためで、雨などの水をはじくようになっています。ちなみに、チョウやガの鱗粉をすべて筆とかを使って落としてしまうと・・・・・ほとんど
透明な羽だけが残ります。つまり、
翅(はね)に鱗粉で化粧している種類ということです。
③
ハエ・カ・アブの仲間(双翅目:そうしもく >>
詳しくはこちら)・・・・・本来、昆虫は
前翅(まえばね)と
後翅(うしろばね)の
4枚の翅(はね)を持つのが普通ですが、
ハエ・カ・アブの仲間では
後翅が退化してしまい、
見た目には翅が2枚しかないように見えるので、この名前がついています。
⑤
セミの仲間(半翅目:はんしもく >>
詳しくはこちら)・・・・・
口の形が針状になっているのが特徴です。翅の根元に近い半分が固く、先のほうの半分が柔らかいために、半分の翅(はね)を持つ種類という意味で半翅目(はんしもく)という名前がついています。
⑧
カマキリの仲間(蟷螂目:とうろうもく >>
詳しくはこちら)・・・・・
蟷螂(とうろう)という字は「
かまきり」とも読まれる字ですが、故事成語では
「蟷螂の斧(とうろうのおの)」として有名です。
卵の形での冬越しや、
メスがオスを交尾後に共食いするという現象で有名です。
⑨ゴキブリの仲間(ゴキブリ目)・・・・・画像リンクはつけませんでした。知らない人はいませんよね。
上記の9つの分類のうち、⑧や⑨は次回で解説する
変態法についての説明に必要なので分けています。
予習シリーズなどでは、
カマキリや
ゴキブリを
バッタ・
コオロギの仲間に入れて
7つに大別しています。昆虫は、
目(もく)レベルだと本来ならもっとたくさんの種類に分類されますが、
①〜⑦が種類の多いグループだと思ってください。
生物を分類する(>>
生物の分類について)ときには、大きな方から、
界・
門・
鋼・
目・
科・
属・
種(かい・もん・こう・もく・か・ぞく・しゅ)と分けて行きますので、①〜⑨の
目(もく)という字は、
項目(こうもく)の目(もく)だと思ってください。では、今日はここまでにします。
2023-01-10
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:理科編
「生物編の植物」についての基礎力を上げる項目に関しては、理科編のその1〜その4で説明したので、次は動物の分類について書いてみたいと思います。植物については、植物のからだのつくりや光合成のしくみなど、まだまだ話をしなければいけないことが多いのですが・・・・・それらは応用編にまわすことにします。
さて動物の分類についても、植物の場合と同様にいくつかの分類法があるのですが、ここで扱うのは、中学入試で一般的な分類法です。
まず、
動物を背骨があるもの(セキツイ動物)と
背骨が無いもの(無セキツイ動物)に分けます。すると、
背骨が無い動物というのは、
イカやタコや貝類、そして
昆虫などの節足動物になるのですが、
中学入試で扱われる内容は、節足動物のみ(特に昆虫)になります。今日は、この
節足動物(>>
こちらを参照)についてみていきましょう。
節足動物は読んで字のごとく、
足に節がある動物のことです。
エビや
カニを食べるときに足がどのようになっているか注意して見てみましょう。
節足動物は足の数によって、昆虫類(足の数が6本)、クモ類(足の数が8本)、甲殻類(足の数が10本他)、多足類(足の数が1体節ごとに2本)の4種類に大別できます。昆虫に関してはもっと詳しく別の回で解説しますが、すべての昆虫は、体が頭部(あたま)・胸部(むね)・腹部(はら)の3つに分かれ、6本の足が胸部(むね)から出ています。
クモ類に分類されるのは、クモ・ダニ・サソリで、体が頭胸部(あたまむね)と腹部(はら)の2つに分かれ、8本の足が頭胸部(あたまむね)から出ています。
甲殻類(>>
こちらを参照)に分類されるのは、エビ・カニ・
ミジンコ(>>
ミジンコについて)などで、体が
頭胸部と
腹部の
2つに分かれているか、頭部と
胸部と
腹部の
3つに分かれている。
10本の足が 頭胸部(あたまむね)や胸(むね) から出ています。 ここからわかるように、
エビや
カニの
ハサミは手ではなくて足であることに注意しましょう。なお、足の本数は10本以外のものもおり、14本の足を持つ
ダンゴムシ(>>
ダンゴムシについて)も甲殻類に含まれます。 また、
プランクトンというのは小さな生物の総称ですから、
ミジンコが甲殻類であることも頭に入れておきましょう。
最後に、
多足類に分類されるのは、
ムカデ(>>
ムカデについて)・
ヤスデ(>>
ヤスデについて)・などで、体が
頭部(あたま)と
胴体(どうたい)の
2つに分かれ、
胴体の一つの体節(たいせつ)ごとに1組(2本)の足が出ています。
なぜ節足動物を最初に扱ったのかというと、現在の動物種の85%以上が節足動物だからです。もちろんこの節足動物の中で中学入試に出題されるのは、ほとんど昆虫に関してなのですが、無脊椎動物の中では節足動物だけをおさえておけば、良いといえます。次回は昆虫について、詳しく見ていくことにします。それでは、今日はここまで。
2022-12-13
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:理科編
前回に続き、中学入試で出題される植物の続きです。前回は面白い習性や名前や繁殖の仕方をする植物を取り上げましたが、今回は特徴が出題される植物をまとめてみました。前回と同じく画像リンクを可能にしてありますので、必ずクリックして見ておいてください。
④覚えておくべき特徴を持つ植物
アサガオ・・・・・ツルは伸びる方向に向かって
右ねじに巻きつく(
上から見ると反時計回り)
ヘチマ・・・・・
お花と
め花の2種類があり、ヘチマの水分は美容液(ヘチマ水)などに、成熟した実を乾燥させた後の繊維はタワシとして使われる。
イチョウ・・・・・オスの木とメスの木があり、メスの木にだけ
ギンナン(銀杏)がつく
ユウガオ・・・・・実を細長く切って乾燥させたものが
カンピョウ。
アサガオ・ヒルガオ・ヨルガオはヒルガオ科だが、
ユウガオはウリ科であることに注意。
トウモロコシ・・・・・
お花と
め花の2種類があり、最近では
バイオエタノールの材料のひとつとして注目を浴びています。
ラッカセイ・・・・・実が
ピーナッツですね。
千葉の名産品であることから、出題されることが多い植物です。
ガマ・・・・・お月見のときに
ススキと一緒に供えるのに使いますね。ガマの穂といわれる部分は雌花が集まったものです。
ウキクサ・・・・・葉と茎が一体となった
葉状体と呼ばれる構造です。
葉緑体と間違えてはいけませんよ。
ホテイアオイ・・・・・花が美しい水草です。よく池や沼に咲いていますね。
葉が丸い形をしていますが、単子葉植物であることに注意しましょう。
A:たくさんの鱗片(りんぺん)に覆われている冬芽
B:1枚の鱗片に覆われている冬芽
C:細かい毛に覆われている冬芽
D:鱗片の表面がヤニで覆われている冬芽
E:鱗片がなく、葉を小さくしたもので覆われている冬芽
*参照元に関しましてはは都合上省略させていただいております。
何卒ご了承下さい。
2022-11-15
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:理科編
前回は「季節と植物」についてを掲載しましたが、今回から2回に分けて、中学入試で出題される面白い植物について書いてみたいと思います。なお、インターネットでこそ可能な画像リンクをつけていますので、必ずクリックして、花の色や形と名前を一致させて覚えておいてください。
(植物の名前をクリックすると参考HP、または参考動画などが新規ウィンドウで開きます。)
①面白い習性を持つ植物
カタバミ・・・・・暗くなると、葉が下に垂れて閉じる。
タンポポ・・・・・日光が当たると花が開き、夜や雨の日には花が閉じている。
スイレン・・・・・明るくなると花が咲き、暗くなると閉じる。
②面白い名前を持つ植物
イヌノフグリ・・・・・実が犬のふぐりに似ていることから命名された。
ホトケノザ・・・・・2種類あるので注意。春の七草のホトケノザ(コオニタビラコ)とは異なる植物。
ハハコグサ・・・・・漢字で書くと母子草。春の七草のゴギョウのこと。
スズメノテッポウ・・・・・雀の鉄砲というぐらいですから、小さい穂がまっすぐ鉄砲のように出ています。
ヌスビトハギ・・・・・名前の由来には諸説あります。漢字では盗人萩と書きます。
ヒャクニチソウ・・・・・百日咲き続けるといわれているのでこの名前がついています。
ヒガンバナ・・・・・秋のお彼岸の頃に咲くのでこの名前がついています。
イヌタデ・・・・・「タデ食う虫も好き好き」ということわざ(人の好みは様々だという意味)がありますが、このときのタデはヤナギタデのことです。ヤナギタデは辛味が強く香辛料として使われます。ところがそれに対して、イヌタデは葉に辛味が無くて役に立たないため、この名前がついたと言われています。
③面白い繁殖の仕方をする植物
A:種子が風に運ばれる植物
B:種子が動物の体について運ばれるもの
C:種子が動物に食べられて運ばれるもの
D:種子が自らの重さで落ちて散らばるもの[ドングリをつける樹木、ドングリの形はよく覚えておくこと]
E:実がはじけて種子を遠くに飛ばすもの
*参照元に関しましてはは都合上省略させていただいております。
何卒ご了承下さい。
2022-10-18
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:理科編
前回は「植物の分類について」書きましたが、その中で、「中学入試で扱われる植物は身の周りで見ることができる植物」だと書いたのを覚えていますか。中学入試の理科や社会で扱われる内容は、基本的には身近なできごとや現象ですから、いつも身の周りでおきている事象に注意を払うことがもっとも効果的な勉強です。というわけで今日は、「季節と植物について」書いていきます。
生物分野:季節と植物について
春の植物
「セリ・ナズナ、ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ、スズナ・スズシロ、これぞ(春の)七草」という覚え方がありますが、これらは1月7日に食べる七草粥の材料となる植物ですから、食草としての役割といえます。ナズナはいわゆるペンペングサ、ゴギョウはハハコグサ、ハコベラはハコベ、ホトケノザはコオニタビラコ、スズナというのはカブ、スズシロはダイコンのことです。
春の植物には、他にもサクラやシロツメクサ(クローバーのことです)、レンゲにツツジにチューリップなどがありますが、植物の名前を訊かれたら、その花の形や色が思い浮かぶようにしておくことが大事ですから、参考書や植物図鑑などで花の色や形をきちんと確認しておきましょう。また、中学入試で出題される植物は、その学校に植えられている植物や近くの公園に咲いている花であることが多いですから、文化祭や学校説明会などで校内を訪れる機会があったら、どんな植物が植えられているのかをチェックしておきましょう。
夏の植物
夏の野原で花が咲く植物は、白や黄色の花をつける植物が多いことを覚えておきましょう。夏の昼間に野原で咲く花は、必要以上の日光を撥ね返すことができるように白や黄色なのかもしれませんね。バラやラベンダー、アザミにユリなどきれいな花をつける植物も多いですが、花が咲く時間帯が出題されるのは夏の植物だといえるでしょう。ちなみに、朝に花が咲くのがアサガオ・タンポポ・ハス・ツユクサ・イネなど、昼に花が咲くのがスイレン、夕方に花が咲くのがオシロイバナとヨルガオ、夜に花が咲くのがオオマツヨイグサやゲッカビジンです。
秋の植物
私の主宰するエクセレントゼミナールでは、秋の七草を「ハギ・キキョウ、クズ・オミナエシ・フジバカマ、ススキ・ナデシコ、秋の七草」という短歌の形式にして覚えさせています。「秋の花は観賞用の花が多く、色とりどりの花をつける」と覚えておくと良いでしょう。秋の七草以外では、コスモス(秋桜)やヒガンバナ(彼岸花)など漢字から連想すると覚えやすい花、イチョウやカエデなど黄葉や紅葉する樹木、クヌギ・コナラ・シイ・カシなどドングリをつける樹木が代表的です。あとは、イヌタデやエノコログサ、オナモミやヌスビトハギの種子などについても覚えておきましょう。
冬の植物
冬の植物は、冬越しと関連して出題されるものがほとんどです。タンポポやナズナやオオマツヨイグサのようにロゼットの状態で冬を越す植物と、サクラ、モクレン、コブシ、ネコヤナギ、ホオノキ、トチノキ、スズカケノキの冬芽(ふゆめ)についてはきちんと判別できるように確認しておきましょう。なぜならば、中学入試が行なわれるのは1月〜2月ですから、冬の植物の姿は出題されることが多いのです。
というわけで、「季節と植物について」は予習シリーズの理科4年上下にくわしく載っていますので、エクセレントゼミナールの生徒諸君はかならずチェックしておきましょう。それでは今日はここまでにしましょう。
2022-09-20
カテゴリー:中学入試に役立つ学習法:理科編
中学入試の理科は、生物分野・地学分野・化学分野・物理分野の4分野に分けることができます。そこで、理科編については分野ごとに単元別に、基礎力を上げるのに必要な知識の確認と暗記法などを取り扱っていきます。
というわけで、今回の内容は、「生物分野:植物の分類について」を扱います。
生物分野:植物の分類について
中学入試で出題される植物は、身の周りで見ることができる植物についてのみ出題されると思ってください。そして、原則としては小学校で扱う植物が基本ですので、種子植物についてのみ出題されると言えます。では、最初に植物の分類がどのようになっているのかを学習しましょう。植物の分類法についてはいくつかの種類があるのですが、ここでは最も一般的な分類のしかたについて書いていきます。
植物は、大別すると種子植物とその他の植物に分けられます。これは、植物がどのようにして増えるかを基準にして分けています。つまり、種(たね)で増えるのか、胞子や分裂で増えるのかで分けるわけです。その他の植物には、シダ植物・コケ植物・藻類(そうるい)があり、これらについて詳しく学習するのは中学以降です。ちなみに藻類(そうるい)の藻(ソウ)という字は藻(モ)と読みますから、プランクトンの〜〜モというのは藻類になります。
種子植物(種で増える植物)はさらに被子植物と裸子植物に分けられます。これは、種をつくるもとである胚珠がむき出しかそうでないかによって分類されています。このうちマツ、スギ、イチョウ、ソテツ、ヒノキなどの裸子植物については中学でくわしく学習することになっています。
ですから、中学入試で出題されるのは被子植物についてのみと考えてください。被子植物は双子葉類と単子葉類に分けられます。つまり子葉(種子の中にはじめから入っている葉のこと)が1枚なのか2枚なのかで分類されているわけですが、これらの植物は一見して見分けることができます。トウモロコシやイネやチューリップなど、葉がとがっている植物(平行脈といいます)は単子葉類で、そうじゃない葉の植物(網状脈)は双子葉類です。このような被子植物のつくりとはたらきは大変重要な単元ですので、別の回でくわしく扱います。
というわけで、植物の分類をまとめたものが下の図ですから、きちんと覚えておきましょう。それでは、また。

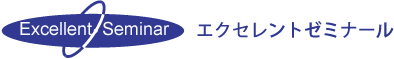



 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム